
THE NORTH ISLAND
welcom to nature of hokkaidou

湿度80パーセントでカビ爆発?暮らしと健康への影響や対策を徹底解説
えっ!というタイトルですが、ひいき目に見ても湿度の80パーセントは高いです。
部屋の湿度が80パーセントを超えると、空気はねっとり重たく、じっとしていても汗ばむような不快さがつきまといます。
そんな環境では、カビやダニの繁殖が一気に加速し、住まいや体への悪影響も深刻になりがち。
押し入れの奥やカーテンの裏に、いつの間にか黒いシミが…なんて経験がある方も多いのではないでしょうか。
この記事では、湿度80パーセントがもたらす実害と、快適な室内環境を取り戻すための対策をわかりやすく以下の項目で解説していきます。
スポンサーリンク
部屋の湿度80パーセントってどんな状態?
湿度が80パーセントに達した室内は、空気が重く感じられ、肌にまとわりつくような蒸し暑さに包まれます。
洗濯物がまったく乾かず、壁紙やカーテンにじっとりと湿気が残ることも。ここまで湿度が高いと「ちょっと不快」では済まず、住環境や健康に影響を与えるレベル。
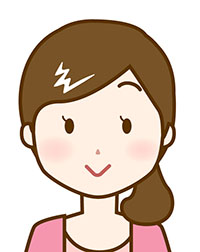
慎重派のアオイ
まずはその数値が示す異常性を確認してみましょう。
どのくらい異常?湿度80パーセントの意味
湿度80パーセントという数値は、日常的な快適ラインをはるかに超えた“異常値”といっていいでしょう。
一般的に快適とされる室内湿度は40〜60パーセント。
70パーセントを超えるとカビやダニが繁殖しやすくなるとされており、80パーセントともなればそのリスクは一気に加速します。
以下の表は各湿度による健康リスクをあらわしたのもで80パーセント~90パーセント以上は危険となります。
| 湿度(%) | 快適度 | リスク指標(0〜10) |
|---|---|---|
| 30% | △乾燥気味 | 2 |
| 40% | ◎快適 | 1 |
| 50% | ◎快適 | 1 |
| 60% | ◯やや蒸し | 3 |
| 70% | △注意 | 6 |
| 80% | ✕危険 | 9 |
| 90% | ✕非常に危険 | 10 |
また、空気中の水分量が多すぎると、体の熱が放出されにくくなり、熱中症のリスクも上がります。
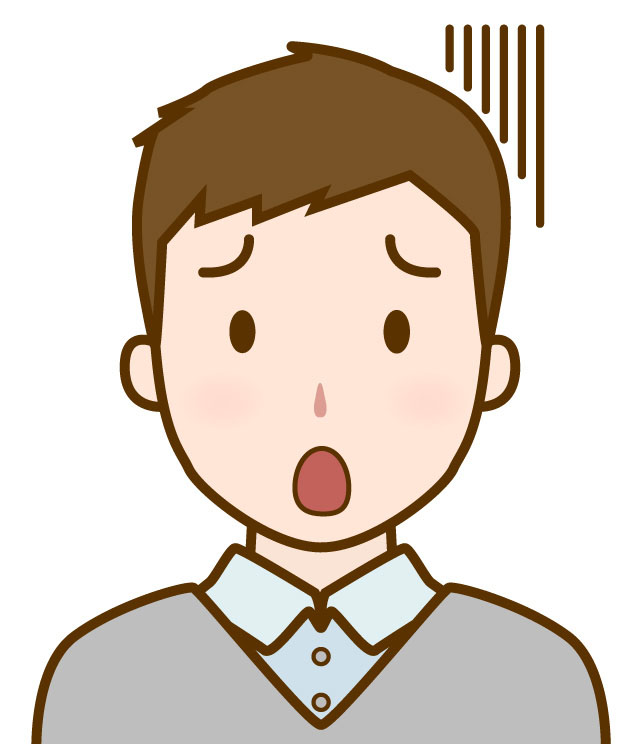
常識派のサトシ
住宅の劣化や電化製品の不調にもつながるため、放置は禁物。
湿度80パーセントは、単なる不快さでは済まない“赤信号”ともいえる状態です。
スポンサーリンク
体に感じる重だるさと熱中症リスク
湿度が80パーセントまで上がると、汗をかいてもなかなか蒸発せず、体温がうまく下がらなくなります。
その結果、体が熱を持ったままこもり、だるさや頭の重さ、めまいといった不調が出やすくなるのです。
特に注意したいのが熱中症。
高温多湿の環境では、汗が乾かないために体の冷却機能がうまく働かず、体内に熱がこもったまま危険な状態へと進行するおそれがあります。
高齢者や小さな子ども、体力の落ちている人はもちろん、健康な大人であっても湿度の高い部屋で長時間過ごせば、脱水や熱中症のリスクが高まるのは避けられません。
「暑くはないのにしんどい」と感じたら、それは湿度のせいかもしれません。

慎重派のアオイ
気温だけでなく、湿度の数値にも目を向けることが体調管理の第一歩になります。
熱中症の予防には温度だけではなく、湿度にも注意をはらう必要があると、慶應義塾大学保健管理センターでも呼びかけています。
熱中症は気温が30℃以下でも湿度が高い場合には発生します。
高湿度の環境では、汗が蒸発しにくいため体温を下げることができずに熱中症の危険が高くなります。
気温30℃かつ湿度80%以上では運動は原則中止、気温30℃かつ湿度30%以上、または気温が26℃でも湿度が60%以上ある場合には激しい運動を避けることが必要です。
引用元 慶應義塾大学保健管理センター HP
スポンサーリンク
家庭で80%になる場面っていつ?

「湿度80パーセント」と聞くと、梅雨の時期や南国の話のように思われがちですが、実は私たちの家庭内でも意外と身近な場面で到達してしまうことがあります。
たとえば、雨の日に窓を閉めきっているとき。
洗濯物を部屋干ししたり、風呂上がりにドアを開けっ放しにしたままにすると、湿気が部屋全体に広がり、あっという間に湿度が上がってしまいます。
また、加湿器を長時間つけっぱなしにした場合や、結露対策が不十分な住宅では、冬でも湿度が80%を超えることも珍しくありません。
特に気密性の高いマンションや新築住宅では、湿気が逃げにくく、湿度がこもりやすい傾向があります。
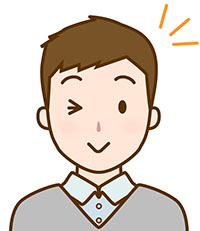
常識派のサトシ
「特別な状況ではないのに湿度が高い」と感じる場合、その原因は日常のちょっとした習慣や構造に潜んでいることが多いのです。
* 理想的な部屋の湿度についての記事もありますので、こちらもどうぞ。
スポンサーリンク
湿度80パーセントで本当に起こる“カビ爆発”
湿度が80パーセントに達すると、見た目にはまだ異常がないようでも、部屋のあちこちで「カビの種」が一斉に動き出します。

慎重派のアオイ
空気中の水分量が増えることで、カビ菌にとって最適な環境が整い、わずか数日で目に見えるレベルにまで繁殖することも。
特に湿気がこもりやすい押し入れ、窓際、カーテンの裏などでは「まさか」の場所にまでカビが広がり、住環境が大きく損なわれてしまいます。
この章では、そんな“カビ爆発”のメカニズムと、放っておくことで生じるリスクについて解説します。
カビが活発に繁殖する条件とは
カビは決して特殊な環境でしか発生しないわけではなく、私たちの生活空間のちょっとした条件が揃うだけで一気に増殖します。
とくに以下の3つの要素が揃うと、カビの繁殖は加速します。
- ・ 湿度70パーセント以上
- ・ 温度20〜30℃
- ・ ホコリや皮脂などの栄養源
カビは気温25〜30℃、湿度70パーセント以上という環境で特に活発に繁殖します。
以下に室温20度~30度時の湿度とカビ発生リスクを表にしたものがありますが、湿度70パーセントを越えたあたりからカビの発生が高まります。

つまり、日本の夏や梅雨時、そして換気が不足しがちな冬の室内などは、まさにカビにとっての楽園と言っていいでしょう。
さらに、湿度が80パーセントに達すると、そのスピードはさらに加速。

常識派のサトシ
空気中の水分量が豊富になることで、カビの胞子が発芽・成長しやすくなり、わずか1〜2日で目に見えるほどのカビが広がることもあります。
特に注意が必要なのは、風通しの悪い場所や水まわり、結露が生じやすい窓枠まわりや、ホコリや皮脂などのカビの栄養源となるものが有る場所。
こうした場所では、一度カビが発生すると根まで入り込んでしまい、表面を掃除するだけでは取り切れません。
カビが好む条件を理解し、予防的に対策することが大切です。
スポンサーリンク
押し入れ、窓際、カーテン裏の危険ゾーンに注意
湿度が80パーセントにもなると、カビの繁殖は家の“見えにくい場所”から静かに始まります。
とくに注意したいのが押し入れやクローゼットの中。
通気性が悪く、布団や衣類から出る湿気がこもりやすいため、気づいたときには木材や壁にカビがびっしり…というケースも少なくありません。

慎重派のアオイ
また、窓際も油断できないスポット。
室内外の温度差で生じた結露が水滴となってたまり、カーテン裏に湿気が集中。
気がつけばカーテンの裾が黒ずんでいた、ということも。
見た目には乾いていても、窓枠のすき間やレールまわりなどはカビの温床になりがちなんですね。
こうした場所は、日常的な掃除では見落としやすく、しかも一度カビが定着すると根が深く、完全に除去するのが難しくなります。
湿度が高い時期ほど、「いつもは見ない場所」にこそ意識を向けておきたいところです。
スポンサーリンク
カビが住まいや健康にも与えるダメージ
カビの被害は見た目の汚れだけにとどまりません。
まず住まいへの影響として、壁紙や木材、畳、布製品などにカビが根を張ることで、変色や素材の劣化が進みます。
放置すれば異臭や腐敗も発生し、賃貸住宅であれば修繕費の対象になることも。
さらに深刻なのは健康への影響です。
カビの胞子は空気中を漂い、私たちの呼吸とともに体内に入り込みます。
これがアレルギー性鼻炎や喘息、アトピー性皮膚炎などの引き金になる場合もあり、特に子どもや高齢者、免疫力の弱い人にとっては深刻な問題に。
また、カビをエサにするダニが発生すれば、アレルゲンの複合汚染となり、症状がさらに悪化する恐れもあります。
カビによる健康被害は、見えないところでじわじわと進行します。
特に問題なのが、トリコスポロンやクラドスポリウムといった空中浮遊性のカビ。
これらは「夏型過敏性肺炎」などを引き起こす原因菌として知られ、繰り返し吸い込むことで慢性的な咳や息苦しさを招くことがあります。
また、室内の空気環境が悪化することで、集中力の低下や倦怠感を訴える人も増える傾向にあります。
アレルギー体質でない人でも、長期間にわたってカビにさらされると、発症リスクが高まるといわれています。
見えないところで静かに進むカビの害。
衛生面でも住宅資産の面でも、早めの対応が肝心です。
スポンサーリンク
ダニとアレルゲンの増加による健康リスク
湿度80パーセントの環境は、ダニにとっても絶好の繁殖条件です。
特に「ヒョウヒダニ」は湿度が60%を超えると活発になり、80%では爆発的に数が増えると言われています。
さらに問題なのは、ダニそのものよりも、フンや死骸が空中に舞い、それが強いアレルゲンになるという点です。
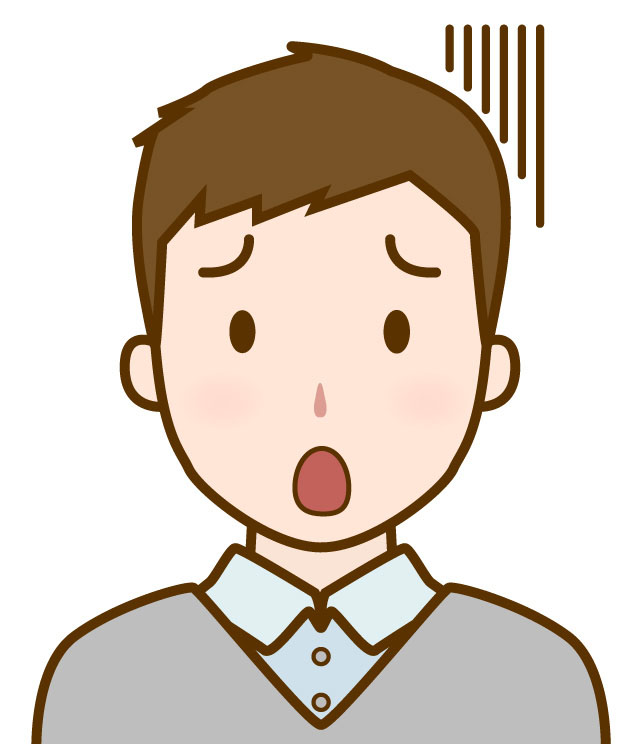
常識派のサトシ
これらは気づかぬうちに吸い込んでしまい、喘息やアレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎などの原因となることも。
特に子どもや高齢者、アレルギー体質の人にとっては大きな健康リスクにつながります。
また、カビと同時にダニが発生しやすいため、アレルゲンが重複することで症状が悪化するケースも少なくありません。
湿度が高い状態を放置すれば、住まいの空気環境はあっという間に悪化してしまいます。
東京都保険医療局でも以下のような注意喚起をしています。
アレルギー疾患の原因や悪化因子となるダニアレルゲンを減らしましょう。
一般に、アレルゲンとなるものには、ダニ、カビ、ペットの毛、 花粉、昆虫、食物などがあります。それらに対してアレルギーに なるかどうかは個人差がありますが、疾患の原因となるアレルゲ ンや悪化因子を避けるための環境整備を行うことも重要です。
・ダニ、カビは湿度の高い環境を好む性質があります。室内、特に壁や床に近い場所の湿度を60%以下にし、アレルゲンとなるダニやカビを増やさないようにしましょう。
・ハウスダストの中にはアレルゲンが多く含まれるため、普段から室内のこまめな掃除と整理整頓に努め、ホコリの溜まる場所を作らないようにしましょう。
引用元 東京都保険医療局 HP
つまり、「湿度80%」という環境は、ダニやアレルゲンの増加リスクが高く、健康被害を引き起こす恐れがあると強く示唆される状態です。
スポンサーリンク
湿度80パーセントの暮らしにさよなら
湿度80パーセントの室内環境は、不快なだけでなく、カビやダニ、そして健康リスクの温床にもなりかねません。
でも、少しの工夫と意識の変化で、ぐっと快適な空間に近づけることができます。
エアコンや除湿器の使い方を見直すだけでなく、家具や窓の配置、観葉植物の置き場所など、ちょっとしたレイアウトの工夫も効果的。
また、湿度計の数字だけを気にするのではなく、自分の体感にも目を向けていくことが大切です。
この章では、湿度80パーセントの暮らしにさよならするための具体的な方法を紹介します。
除湿器・エアコンの効果的な活用法
湿度80パーセントを下げるには、やはり除湿器やエアコンの力を借りるのが最も手っ取り早い方法です。
除湿器は、空気を冷やして水分を取り除くことで除湿する「コンプレッサー式」。
乾燥剤に水分を吸着させて除湿する「デシカント式」などタイプによって得意な季節が異なるため、使用環境に合ったものを選ぶことが大切。
なので夏は室温が高いほど除湿能力が高まるコンプレッサー式、冬は室温が低い環境でも安定した除湿能力を発揮するデシカント式が向いています。
たとえばこの機種はコンプレッサー式で夏向きといえます。
スポンサーリンク

除湿機 シャープ コンプレッサー式 CV-R71-W ホワイト系 SHARP (木造8畳/コンクリ16畳まで)プラズマクラスター7000 衣類乾燥 省エネ コンパクトサイズ 省スペース コンプレッサー 除湿器【 CV-P71 の後継 】消臭 清潔 cvr71 CVR71
一方、エアコンの「ドライモード」は広範囲を一気に除湿できる便利な機能。
ただし、冷房と違ってあまり温度が下がらないので、寝室などにもおすすめです。
どちらを使うにしても、閉めきった空間で使うのがポイント。ドアや窓が開いていると、除湿効果が半減してしまいます。
うまく使い分けて、効率的に湿度をコントロールしましょう。
スポンサーリンク
間取り・家具・窓のレイアウトの工夫
湿度が高い部屋では、空気の流れが悪くなることで湿気がこもり、カビや結露の温床になります。
とくに家具の背面や窓まわりは要注意。
壁にぴったりくっつけて配置すると空気が循環せず、カビが発生しやすくなります。
できれば壁から5cm以上のすき間をあけて設置しましょう。
また、押し入れやクローゼットの中も通気性を意識することが大切です。
すのこを敷いたり、収納ケースを床から少し浮かせたりすると湿気対策になります。
窓際には家具や厚手のカーテンを密集させすぎず、風の通り道を確保するのもポイント。
空気の流れを意識したレイアウトは、除湿器やエアコンの効果を高めるうえでも効果的です。
住まい全体の空気が「動く」ことを意識してみてください。
部屋の空気を動かし、湿度を均一にするためには、こんな扇風機なんかがお勧めです。
スポンサーリンク

サーキュレーター アイリスオーヤマ 首振り リモコン付き 静音 梅雨 コンパクト 18畳 節電 省エネ 節電 上下左右首振り 軽量 PCF-SCC15T-D電気代節約 送料無料 扇風機 お手入れ簡単 おしゃれ 部屋干し リズム風 室内換気 暖房 空気循環 おしゃれ ギフト
換気・室内干し・観葉植物への注意点
高湿度の原因は「換気不足」や「生活習慣」に潜んでいることも少なくありません。
とくに雨の日や冬場は窓を閉め切りがちですが、1日に数回、数分でも空気を入れ替えるだけで湿気の滞留は大きく防げます。
また、室内干しにも注意が必要。洗濯物からは多くの水分が蒸発し、部屋の湿度を一気に押し上げてしまいます。

慎重派のアオイ
除湿器や換気扇を併用し、できるだけ風通しの良い場所を選ぶのがポイント。
観葉植物も湿度に影響を与える存在です。
水やり後の蒸散や鉢まわりの湿気が積もり積もってカビの原因になることもあるため、置きすぎには注意しましょう。
インテリアを楽しみつつも、湿度のバランスを意識することが快適な空間づくりにつながります。
スポンサーリンク
「数値」だけじゃなく「体感」も大事

湿度計で数値を確認することは大切ですが、最終的に頼りになるのは自分の感覚です。
湿度が60パーセントでも「じめっとしている」「寝苦しい」と感じる日もあれば、70パーセントでも快適に過ごせることもあります。

常識派のサトシ
これは気温や風通し、服装、活動量などが複雑に関係しているからです。
また、湿度計の設置場所によっても数値は大きく変わります。
窓際や加湿器の近くだと実際より高く出ることも。
数字にとらわれすぎず、「肌がべたつく」「布団が湿っぽい」といった小さな体感をヒントに、対策を取っていくことが快適な空間づくりの近道です。
数字と感覚のバランスをとりながら、無理なく湿度管理をしていきましょう。
スポンサーリンク
湿度80パーセントでカビ爆発? あとがき
夏場の湿度80パーセントって僕のような北海道民にとってはキツイですね~
20代のときに会社の研修で8月の東京で2週間ほど過ごしましたが休みの日はホテルから出ずに部屋にこもりっきりでした。
気温は連日30度オーバーで湿度は80パーセント前後、北海道の体感から比べると湿度がまるで違うので温度は+5度の体感。
地元の社員の中には北海道から転勤した者もいて「慣れるよ。」とは言っていましたが、僕は内心ムリと思っていました。
あれから40年以上経ち現在の北海道の夏も日によっては温度30度を超え、湿度も80パーセントに近くなることもあります。
僕が子供のころは、北海道では必要を感じなかったエアコンも、今では普通に夏の必要アイテムとなっています。
肌感覚としてはここ北海道も確実に夏の気温や湿度が高くなってきているのを感じます。
その原因が温暖化のせいなのか、何なのかは分かりませんが、とにかく暑くなっている。
この記事を書いている今日も6月の北海道としては珍しく30度越えの地点が何か所かありました。
ですが湿度は60パーセントほどで、典型的なカラッとした夏の北海道という日です。
とにかかく、これからの高温多湿の季節、体調には気を配り健康に過ごしましょう。
* その他の湿度関連の記事もありますので、こちらもどうぞ。
🔗 湿度が快適なのはどのくらい?温度も含めた適正湿度はこれだ!
🔗湿度10・20・30パーセントは乾燥注意!体への影響と対策とは
🔗湿度40パーセントは本当に快適?乾燥リスクと体への影響を徹底解説!
🔗湿度50パーセントは本当に快適?体感・温度・不快指数をわかりやすく解説
🔗湿度60パーセントの暮らしってどう?体感・カビ・快適度をチェック
🔗部屋の湿度70パーセントは高い?春夏秋冬の最適湿度を見てみよう
🔗湿度70パーセントは危険信号?カビのリスクと暮らしの注意点を総点検
🔗湿度90パーセントの体感 それって雨、暑い、髪の毛はどうなる?
スポンサーリンク
🔗 TOPに戻る




